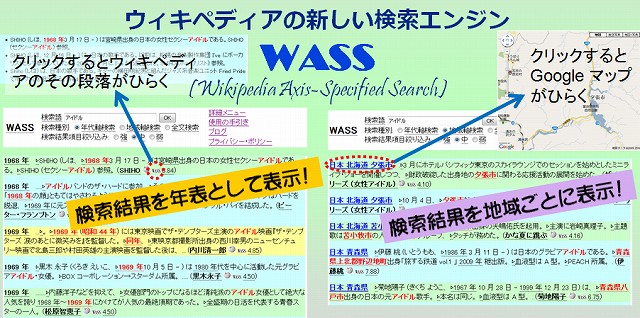産業・ビジネス アーカイブ
0001-01-01
2007-08-31
シャドーワークとはなんなのか結局わからず ― 一條 和生 著 「シャドーワーク―知識創造を促す組織戦略」
シャドーワークということばをつくったイヴァン・イリイチによるその定義は 「無報酬とされている仕事だが,何らかの経済行動の基盤を維持したり,支援したりするために不可欠な仕事」 だという. 本書の著者はシャドーワークをはっきり定義していないが,「上司の指示を待ったり,事前に相談したり,または許可を受けるようなことをせずに,自発的な非正規の行動を起こすこと」 がシャドーワークだと書いている. これはイリイチの定義とはあきらかにちがっていて,しかも,とくに 「非正規の行動」 というところがあいまいである. 本書でとりあげられている例をみると,著者がいう 「シャドーワーク」 には無報酬のものもあり報酬があたえられているものもある. また,仕事じたいも経済的に支援されているばあいとそうでないばあいとがある. 無報酬だったり支援されなかったりするときは,その 「仕事」 と会社との関係はよわくなるとかんがえられるが,本書では会社との関係がつよいケースばかりがとりあげられている. 私にはとりあげられている例の大半は本来のシャドーワークにあたらないようにおもえる. はっきり定義されていないことからもわかるように,著者にとっては実はシャドーワークという概念はたいした意味をもっていない,むしろ仕事における自発性に興味があるのだとかんがえられる. シャドーワークそのものに興味があった私は失望させられた.
評価: ★★☆☆☆
関連リンク:
シャドーワーク 知識創造を促す組織戦略@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
シャドーワーク 知識創造を促す組織戦略@Amazon.co.jp
,
シャドーワーク 知識創造を促す組織戦略@Amazon.co.jp.
2007-10-13
あまりに夢のない未来 ― 夏野 剛 著 「ケータイの未来」
冒頭に 2020 年におけるケータイのつかわれかたをえがく 「小説」 が書かれているが,それを読んでいきなり,がっかりさせられた. そこに書いてあることは,研究レベルではいますでにほとんど実現されていることである. まったく夢が感じられない. しかし,著者はつぎのように書いている. 「人間の基本的なライフスタイルや考え方は,半世紀単位でも思ったほど変わっていないように思える. [中略] 今現在の生活者である我々がピンと来ないものは,10 年 ~ 20 年経ったとしても使われることはないのではないだろうか.」 冒頭の小説はこのかんがえにもとづいて書かれたということだろう. 通信インフラとして出発し i モードによって IT インフラとなったケータイだが,現在すでに,おさいふケータイがだいぶ普及し,つぎのステップはそれを 「生活インフラ」 にすることだという. 日本ではまだクレジット・カードが普及していないというところに目をつけて,それをケータイのうえで実現しようという戦略はしたたかなものである.
本書でおもしろいところは,第 3 章におけるテレコム業界批判である. 顧客ではなく 「業界のため」 を第 1 にかんがえる体質やをするどく批判し,それにたちむかったことで i モードを成功させたと自負している. また,WAP (ケータイ Web 標準) に関して,標準化会議における日本人の影の薄さを指摘している. また,技術の優位性こそすべてという 「技術単独信奉」 を批判し,FOMA においてそれが成果をあげたことをのべている. ほかにもおもしろい内容がふくまれているが,ここまでにしておこう.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
ケータイの未来@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
ケータイの未来@Amazon.co.jp
,
ケータイの未来@Amazon.co.jp.
2007-10-28
みせしめによる倒産・破産の是非
山一証券以来,不正をおこなった企業が政府機関の処分をうけて倒産・破産する事件がつづいています. もうだいぶまえのことりなりますが,ライブドアと村上ファンドはだれの記憶にものこっているでしょう. 最近ではコムスンや NOVA (ノヴァ,ノバ) があります. これらの企業のなかには行政処分の内容によっては事業撤退をまぬがれたケースもあるのではないでしょうか. 処分によってその企業だけでなく顧客までおおきな影響をうけていますが,顧客である国民までまきこむ,きびしすぎる処分がおこなわれているようにおもわれてなりません.
2007-12-02
個人ごとのニーズにこたえていた HP 社のオフィス ― 共同開発での経験
私は 「2 つの他社での経験 ― ドキュメントに関するかんがえかたのちがい」 という項目にも書いたように,2000 年に会社から Hewlett Packard (ヒューレット・パッカード社, HP) 社に 1 カ月ほど “派遣” されて,共同開発のプロジェクトにたずさわったことがあります. HP 社には日本の会社にちかい部分もあって,そのために共同開発がうまくいっているという面もあるようにおもいますが,もちろん,ちがうところもいろいろあります. もうずいぶんまえのことになってしまいましたが,いままで書く機会がなかったので,そのとき感じたことを書いてみたいとおもいます.
2008-03-11
よく書かれているがあたらしい発見はいまひとつ ?! ― 林 信行 著,「アップルの法則」
アップル (Apple) はどういう会社か,またスティーブ・ジョブスはどういうひとか,それを新書というみじかい本のなかにうまく書いている. とくに,ジョブスがどうやってアップルという会社をとりもどしたのか,その後どのような戦略をとっているかなど,もしまだ知らなければ読む価値があるだろう. しかし,すでにある程度こうした知識を知っている私にとっては,おさらいにはなったが,いまひとつ,あたらしい発見はなかったようにおもう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
アップルの法則@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
アップルの法則@Amazon.co.jp
,
アップルの法則@Amazon.co.jp.
2008-04-12
コンテンツ法制改革としての 「通信と放送の融合」 ― 中村 伊知哉 著,「「通信と放送の融合」 のこれから ― コンテンツ本位の時代を迎えて法制度が変わる」
これは,「通信と放送の融合」 に関する本というよりは,コンテンツ政策に関する本である. 日本特有のポップカルチャーがうみだすコンテンツに目をむけ,それをいかすコンテンツ政策を提言している. 通信と放送との区分は日本特有の法制からくるものである. イギリスのコンテンツ配信事業者からは 「伝送方式で制度の適用が異なり,著作権処理の扱いも異なる,という日本の事情が一笑に付された」 (p. 192) という. つまり,「通信と放送の融合」 というのは技術的な課題ではなくて,こういう法制をあるべきすがたになおしていくことだということだろう.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
「通信と放送の融合」のこれから@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
「通信と放送の融合」のこれから@Amazon.co.jp
,
「通信と放送の融合」のこれから@Amazon.co.jp.
問題の根深さを痛感する ― 田中 克己 著,「IT 産業崩壊の危機 ― 模索する再生への道のり」
BK1 の内容説明によると 「日本の IT 産業が崩壊の危機に瀕している. 牙を剝くグローバル競争の脅威.富士通,NEC,日立はどう立ち向かうのか.産業構造の変革期にあることを改めて訴え,次の IT 産業を創出するための 「カギ」 を提示する.」 ということだが,実はまったく解決への方向を提示できていない. Amazon.co.jp の書評をみても,意見はまったくバラバラであり,問題の根深さを痛感する. しかし,それはすくなくともこの本が問題点の指摘においては成功していることを意味している.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
IT 産業崩壊の危機@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
IT 産業崩壊の危機@Amazon.co.jp
,
IT 産業崩壊の危機@Amazon.co.jp.
2008-04-24
物理屋のための (?!) イノベーション論 ― 山口 栄一 著,「イノベーション ― 破壊と共鳴」
著者は農地地価などのデータを入手して,それをみずからコンピュータで分析し,十勝地方に 「特異的に,農業が産業として成立」 していることをみいだした. そして,その謎をとくために現地にでかけて取材している. こうした努力の末に書かれたのがこの本である. この本の最後では国政における自民党と民主党,有権者の行動なども分析されている.
とはいっても,この本がおもにあつかっているのは半導体材料におけるイノベーションである. みずからもかつてつとめていた大企業でイノベーションのたねが死蔵されている状態からぬけだすカギをもとめて,有名なクリステンセンの理論に異をとなえている. とはいえ,物理屋でも半導体屋でもないソフトウェア屋の私には,ここからイノベーションをおこすカギをみつけるのはむずかしい.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
イノベーション 破壊と共鳴@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
イノベーション 破壊と共鳴@Amazon.co.jp
,
イノベーション 破壊と共鳴@Amazon.co.jp.
2008-04-20
世界の急速な変化と日本人のすすむべき道
この 10 年くらいのあいだに世界は急速に変化し,今後も急速な変化がおこることが予測されています. ここ 10 数年,日本は停滞した状況にありましたが,それゆえに世界との関係はかえって急速に変化し,それにともなって今後は日本も急速に変化することが予想されます. こういうなかで,我々はどちらにすすむべきなのでしょうか? すこしかんがえてみたいとおもいます.
2008-04-24
電力ネットワークのふしぎ
通信ネットワークにおいては,受信した情報は通常はだれか特定のところで発信されたものであり,おおくのばあいに発信者を特定することができます. ところが,同様のネットワークによっておくられてくる電力に関しては,どこからおくられてきたものかを特定することができません. にもかかわらず,とくに欧米などでは環境に配慮した特定の発電者から電気を買うことができるようになってきています. これはふしぎなことだとおもえます.
2008-04-29
脇役としての情報通信技術
すくなくとも最近まで,情報通信技術は最先端技術であり,主役でした. すくなくとも情報通信技術者たちは,そうおもっていたでしょう. しかし,ユビキタスの時代,つまりコンピュータがみえなくなる時代 (「ユビキタス・コンピューティングとエージェント指向コンピューティング」 参照) には,もはやコンピュータは主役ではなくなる,つまり情報通信技術は主役である 「みえる技術」 をささえる脇役になるのだとおもいます. 主役はむしろ農林水産業や鉱業などなのではないかともおもいます.
2008-04-28
分散型電力で安定な供給ができるか? ― 合田 忠弘 他著,「マイクログリッド ― 分散型電源と電力ネットワークの共生のために」
マイクログリッドの厳密な定義はこの本にゆずるが,それは従来の電力ネットワークに接続される分散した電力供給者と消費者とで構成される. 家庭の太陽光発電システムもマイクログリッドの一部になりうるが,この本がおもな対象としているのはもうすこし大規模な,企業などの発電システムであり,発電機器としてもマイクロ・ガスタービン,マイクロ・ガスエンジンなどがとりあげられている.
世間では太陽光発電に関しても CO2 が削減されるといった利点ばかりが強調されているという印象をうける. しかし,カリフォルニアやニューヨークでかつて発生した停電は,電力の安定供給がそんなにかんたんなものでないことをしめしている. 分散型の発電がひろまれば,電力系が不安定になるのではないかという私の疑問に,この本はこたえてくれた. ひとことでいえば,これから解決するべき課題が山積しているということである. 理系の私にもわかりにくい技術的な内容をふくんでいるが,おおまかな把握のためにはやくにたつとおもう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
マイクログリッド@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
マイクログリッド@Amazon.co.jp
,
マイクログリッド@Amazon.co.jp.
2008-05-06
この本のオリジナリティはどこに? ― 大宮 知信 著,「ひとりビジネス ― 転身・独立で幸せをつかむ」
読んだことはないが,「1人ビジネス」 に関する本はすでに何冊か出版されている. また,雑誌にはいろいろ紹介されている. この本はいろいろなケースがとりあげられていて,よくまとまっているとおもう. しかし,すでにいろいろ同様の情報があるなかで,なぜいまこの本を出版したのか,よくわからなかった. もっとオリジナリティをはっきりだしてほしかったとおもう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
ひとりビジネス@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,ひとりビジネス@Amazon.co.jp
,ひとりビジネス@Amazon.co.jp.
実力主義,成果主義などへの不当な非難 ― 藤本 篤志 著,「御社のトップがダメな理由」
著者は日本の会社に導入された 「実力主義」,「成果主義」,「360 度評価」,「フラット型組織」,「ボトムアップ主義」 をつぎつぎと斬っていく. これらは手本となった国の企業ではうまく作用していたのだろうが,それを国情や社風などのちがいに十分配慮せずに導入したために失敗した例が多々あるのは事実だろう. しかし,この本の論旨には飛躍しているところが多々あるようにおもう. たとえば実力主義は野心家に悪用されるからよくないということが書かれているが,それがどういう条件のもとでおこるかは分析されていない. 全体を通じて感じるのは,きちんと分析しないまま,わるい面ばかりが強調されていて,うまく導入すれば機能する上記の主義たちが不当にけなされているということである.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
御社のトップがダメな理由@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,御社のトップがダメな理由@Amazon.co.jp
,御社のトップがダメな理由@Amazon.co.jp.
2008-05-12
ヒントはいろいろあるが,セキュリティの検討がないのが弱点 ― 吉田 健一 著,「エンタープライズ 2.0 ~次世代ウェブがもたらす企業変革~」
Web 2.0 の技術をどのように企業活動にいかすことができるか. 本書はその概論をのべ,ブログ,SNS,Wiki など,さまざまな Web 2.0 の手段について個別に検討してもいる. そこから,いろいろなヒントをよみとることができるだろう. しかし,本書においては現代の企業にとって最重要課題のひとつであるセキュリティに関する検討がまったくおこなわれていない. セキュリティに関する指針がないままでは,企業がこれらの手段をとりいれることはできないだろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
エンタープライズ 2.0@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,エンタープライズ 2.0@Amazon.co.jp
,エンタープライズ 2.0@Amazon.co.jp.
“海賊” から水産資源をまもる必要がある
日本はまわりを海でかこまれているため,過去には国や陸上の資源をまもるのはむしろ容易だったということができます. おおきな船をつくることがむずかしかった時代に,船で日本までやってくるのは容易でなかったからです. ところが,せまい国土におおくのひとがすむ日本にとって,日本をかこむ広大な経済水域にある魚貝類や海底資源は貴重な資源です. ところが,これらは海賊などによってうばわれる危険があります. 道がなければ容易にはいることができない陸地とはちがって,海はどこからでも船ではいりこむことができます. 大型船で資源を根こそぎ,もっていくことも比較的容易です. 一方,それをふせぐのは容易ではありません. 今後,資源をまもるためには周到な防衛体制が必要になるでしょう.
2008-05-17
大河ドラマの篤姫は副社長 ?!
NHK の大河ドラマにおける篤姫は,当時の日本においては自分ですすむ道をきりひらくことはできず男にしたがうしかないということをみとめつつも,できる範囲で自発的にかつ積極的にふるまっています. いわば,社長にはしたがわざるをえないが自分の権限の範囲ではおおなたをふるえる “副社長” として,最大限の努力をしているようにみえます. それはあたかも現代の企業における経営者 (副社長) のようにえがかれているように私にはみえます.
安全標語 / 川柳
会社では毎年,安全標語 / 川柳 が募集されています. ノルマをはたすため,つぎのようなのをつくりました.
雨あがり すべらぬさきに 見る足元
最低限の時間しかかけないので,あまりほこれるものではありませんが,記録のためにここに書いておきます.
2008-05-23
人物中心で経営や技術の記述には不満がある ― 山口 敦雄 著 「楽天の研究 ― なぜ彼らは勝ち続けるのか」
楽天の取締役たちへのインタビューを中心として,楽天の経営者のひととなりをうきぼりにしている. それをつうじて楽天の経営方針などもしめされるが,人物をえがくことが中心であるため,技術についてはほとんど書かれていないし,経営についての記述も散漫な印象をうける. 「楽天の研究」 というタイトルをつけるからには,もうすこしひろくカバーしてほしいとおもう.
評価: ★★☆☆☆
関連リンク:
楽天の研究@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,楽天の研究@Amazon.co.jp
,楽天の研究@Amazon.co.jp.
2008-06-04
クタバれ! 本のランキング
きょうの NHK 「クローズアップ現代」 によれば,最近は本をランキングだけで選択するひとがおおいということです. 年に数冊しか本を買わないひとが,とくにランキングをたよりに本をえらぶという話でした. そのために書店もランキングばかりにたよるようになっているとのこと. そんな書店はクタバってしまえばよいのです. ランキング下位の本もそろっていて,かんたんにその情報にアクセスすることができるオンラインの書店で買うほうがずっとよい. 独自の基準をもって本を選択し,ならべている書店だけが存在する価値があるとおもいます.
2008-06-03
ひとりで仕事をしたい (?!)
複数人・複数組織での仕事は,自分あるいは自社がうまくいっても,ほかで コケると全体がうまくいかなくなってしまいます. こんなことを書いてもグチにしかならないとはおもいますが,趣味と同様,仕事もひとりで閉じることができれば,他人のためにダメにされることはないのに…とおもってしまいます. 会社のなかではなかなか,おもうようにはいきませんが,会社のひとや秘密にかかわらないことはなるべく会社からはなれて,ひとりで,自分の趣味にあうやりかたでやりたいとかんがえています.
2008-06-07
石油価格高騰を機に鉄道による貨物輸送を復興させよ!
最近,石油価格が急激に上昇しています. 投機によって需要以上に値上がりしたぶんはいずれさがるでしょうが,需要そのものが大幅にふえている以上,それほどさがることは期待できません. そういうなかで,これまでトラックにたよってきた国内の貨物輸送はコストが上昇しています. くるしんでいるトラック輸送業界にさらに追い打ちをかけることにはなりますが,これは石油の消費がすくなく CO2 排出もすくない鉄道輸送を復興させるチャンスなのではないでしょうか?
宅配寿司 ― 店によるちがい
さまざまな宅配業者があります. ピザの宅配はアメリカでも日本でも人気がありますが,最近は寿司の宅配がふえているようにおもいます. こどもが寿司をこのんでいる関係で比較的つかうことがおおいのですが,いくつかの店をためして,わかってきたことがあります.
2008-06-12
ナイーブな印象 ― 三木谷 浩史 著 「成功のコンセプト」
経済が低迷する 1990 年代に楽天で大成功をおさめた著者は,きっと,成功するための策をいろいろかんがえぬいたにちがいない. 読むまえには,「成功のコンセプト」 というタイトルの本であれば,そういうことがぎっしり書いてあるにちがいないとおもっていた. しかし,ここにつづられているのは,「僕にとってこの [ハーバード大学のビジネススクールへの] 留学のいちばんの収穫は,MBA を取得したことより起業精神に触れたことだ」 (p. 79) ということばに象徴されるように,むしろ非常にナイーブな印象をうける. 三木谷本人が書いた本であるがゆえに,よりつよくそういう印象をうけるのだろう. そこが,小手先の策を弄しつづけたホリエモンとの一番のちがいなのだろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
成功のコンセプト@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,成功のコンセプト@Amazon.co.jp
,成功のコンセプト@Amazon.co.jp.
食い足りないがエピソードはおもしろい ― 児玉 博 著 「“教祖” 降臨 ― 楽天・三木谷浩史の真実」
この本のタイトルからは,いかがわしい雰囲気がつよく感じられる. しかし,内容は三木谷のおいたちから興銀就職,MBA 取得,孫正義との出会い,楽天のたちあげ,楽天球団誕生,フジテレビ問題などをまじめに論じていく. なぜこのようなタイトルをつけたのか,不明である. 三木谷と孫,ホリエモンなどとの関係やちがいの記述をはじめ,おもしろいエピソードはいろいろ書かれているが,280 ページほどのなかであまりにおおくのことを書いているので,食い足りないのはやむをえないだろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
“教祖” 降臨@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,“教祖” 降臨@Amazon.co.jp
,“教祖” 降臨@Amazon.co.jp.
2008-06-17
土地の仲介手数料と司法書士の報酬額の幅
土地のとりひきをするとき,業者に仲介をたのむと,当然のことながら手数料がかかります. また,土地の登記やローンのための抵当権設定は司法書士にたのむ必要があり,そこでは税金 (登記料など) とともに司法書士への報酬がかかります. これらの費用をできるだけおさえたいので,いろいろ交渉し,まだ交渉中のものもありますが,そこで,いろいろなことがわかってきました.
2008-06-20
この本の 「ものの見方」 にまなぶべし! ― 博報堂生活総合研究所 著 「タウン・ウォッチング ― 時代の 「空気」 を街から読む」
まちやそのなかの店をその構造やひとのながれ,時間帯など,さまざまな角度から分析・分類している. とくに,それらの分類のしかたや概念につけられた 「わざわざ店」,「エキサイティングショップ」 などのなまえに,学術的な分析とはちがう博報堂らしさがある. 内容はもうだいぶふるくなってしまっているが,ここでしめされている 「ものの見方」 にはまなぶべき点がおおい.
評価: ★★★☆☆
2008-06-23
新銀行東京にチャンスがやってきた ?!
新銀行東京は 「失われた 10 年」 のなか,銀行が貸ししぶる中小企業を対象とした融資をすることを目的として設立された. しかし,設立されたときにはすでに既存の銀行も中小企業への融資を積極的におこなうようになっていた. そのためこの銀行はおおきな損失をだして苦境におちいり,その存在意義がとわれるようになっていた. しかし,いま,経済はふたたび不況にむかいつつあるようにみえる. そのなかで,また他の銀行は中小企業に貸ししぶるようになってきている. これは新銀行東京にとってチャンスというべきだろう.
社会起業家によって経済成長がもたらされたバングラデシュ
最近,日本では 「社会起業家」 とよばれるひとたちがふえてきて,徐々に日本の社会や経済をかえようとしている. しかし,現在はまだそれほどおおきなちからをもってはいないとかんがえられる. しかし,バングラデシュにおいては 「社会起業家」 が銀行をつくり,零細な企業にまで融資することによって,政府にたよらずにたかい経済成長を実現させているという.
2008-06-21
2008-07-02
絶大な,あいみつもりの効果 ― 司法書士とひっこしと
「土地の仲介手数料と司法書士の報酬額の幅」 という項目で,土地取引などで必要になる司法書士への報酬額について書きました. 2 人の司法書士からあいみつもりをとりました. その効果は絶大でした. 最初にもらったみつもりのまま依頼するのにくらべると 44% も節約することができました.
2008-06-30
テレワークの負の面 ― 佐藤 彰男 著 「テレワーク ― 「未来型労働」 の現実」
テレワークに関してはその正の面ばかりを書いた本がおおいが,本書はその負の面を冷静に分析している. 正の面について書いた本とあわせて読むことによって,テレワークをよりよく理解することができるだろう.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
テレワーク@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,テレワーク@Amazon.co.jp
,テレワーク@Amazon.co.jp.
2008-07-11
KT 法による問題の詰めかたとひらめきなど ― C.H.ケプナー, B. B. トリゴー 著 「新・管理者の判断力 ― ラショナル・マネジャー」
本書は有名な KT 法の原典である.系統的な問題解決の方法を記述している. この方法は,状態把握,問題分析,決定分析,潜在的問題分析という 4 つの 「ラショナル・プロセス」 からなっている. 本書を読めば,これらのプロセスをどのように適用すればよいか,そのおおすじがわかる.
本書のもっとおもしろいところは,これらのプロセスの適用例として,おおくの実例がとりあげられていることである. これらの実例を理解することによって,KT 法をどう適用すればよいか,そのヒントをえることができる. 本書が書かれた時代のためだろうが,これらの例のおおくは生産現場や顧客への出荷にともなって発生した問題をとりあげている.
しかし,これらの実例をみると,それらにおいては KT 法によって必然的に問題が解決できたわけではなく,おおくのばあいにひらめきや常識にとらわれない判断などがきっかけとなって問題が解決されていることがわかる. 系統的に問題を詰めたことがこれらのひらめきや判断につながったのだろうが,KT 法以外のやりかたをとったときにくらべてよかったのか,わるかったのかは,これだけでは判断できない.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
新・管理者の判断力@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,新・管理者の判断力@Amazon.co.jp
,新・管理者の判断力@Amazon.co.jp.
経営雑誌にもとりあげられる篤姫
最近,篤姫についていろいろ書いていますが,「大河ドラマの篤姫は副社長 ?!」 という項目では 「経営改革」 をすすめる篤姫を副社長になぞらえました. その後のドラマにおいては篤姫が信念にしたがって行動するさまがえがかれていますが,これもまた,経営者にかぎらず現代社会においても重要なことです. 「プレジデント」 など,経営者むけの雑誌ではよく徳川家康などの歴史上の人物がえがかれていますが,篤姫もとりあげられてしかるべきなのではないかとおもってみたところ,すでにとりあげられていました.
2008-07-24
三菱…銀行と Bank of Tokyo ... ― 単純に 「東京銀行」 とすればよい!?
日本のおおくの銀行は,合併によってめまぐるしくなまえをかえてきた. 三菱東京 UFJ 銀行もそのひとつである. ひとつまえのなまえは東京三菱銀行だったのに,「東京」 と 「三菱」 とがいつのまにか,ひっくりかえっている. しかし,英語名はいまも Bank of Tokyo ではじまり,あまりかわっていない. いっそ,日本名も 「東京銀行」 にすればよいのではないだろうか?
2008-07-20
大型店が諸悪の根源 !?
三浦 展 や共著者たちは 「ファスト風土化する日本」,「下流同盟」 などの本において,アメリカではウォルマートがまちをこわし,あちらこちらでその出店につよい反対運動がおこっているとのべている. ウォルマートの出店が地元の商店街をだめにし,非正規雇用をふやして低賃金ではたらかせ,まち全体をだめにしてしまうという. また,生産者への徹底的な値下げ要求によって,工業などにも影響をあたえている. 日本ではジャスコがウォルマートにちかいやくわりをはたしている.
2008-08-08
中野南部,あちこちに立つツインハウス
中野区の南部,川島通りと富士高校とのあいだの道に 3 対の “ツインハウス” があります. ツインハウスとは,もともと 1 件の家やひとつのビルがたっていた土地を 2 つにわけて,よく似た 2 件の家をたてたもののことをいっています. 以前ならこうした土地にはビルをたてたりアパートをたてたりしたところですが,最近ではちいさな一戸建て住宅をたてることがおおくなっているわけです.
2008-08-18
アメリカ流合理主義にもとづく流通論 ― 渥美 俊一 著 「流通革命の真実 ― 日本流通業のルーツがここにある!」
著者は読売新聞記者出身ではあるが,1960 年代から大規模小売店業者を指導する立場になった. 本書はその立場から書かれたものである. 本書においてはアメリカの合理主義的なやりかたを紹介し,それが日本に根付かないことをいろいろな点から指摘・批判している.
たとえば,「有機栽培だから」,「自然農法だから」 よいといいつつ,その科学的根拠があいまいにされている点 (p. 71),マクドナルドのマニュアルが科学的実験をつきつめてできあがっていること (p. 202),台湾での買い付けにおいてアメリカのバイヤーが品質確保のためにきちんと指示をだしているのに日本のバイヤーはそれをしていないために品質が確保できていないこと (p. 241),日本のアイロン台は丈夫すぎて高価になっていること (p. 203) などが指摘されている.
しかし,アメリカと日本とのちがいやアメリカでウォルマートがきらわれていることなども考慮するべきだとおもえるが,こうしたことについてはほとんど書かれていない. アメリカの業界は日本より消費者を指向しているが,この本においては消費者の立場をどうかんがえているのかもあきらかでない. というわけで疑問の点もいろいろあるが,まだ,くみとれる点もおおいとかんがえられる.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
流通革命の真実@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,流通革命の真実@Amazon.co.jp
,流通革命の真実@Amazon.co.jp.
はばひろい原因・レベルに適用できる対策がしめされている ― 浜口 直太 著 「仕事がどんどん面白くなる やる気の法則」
「やる気」 がないのにもいろいろな原因やレベルがある. この本ではその原因を 「思うように仕事がはかどらないから」,「仕事の目標が見つからないから」 など,6 つに分類している. そして,原因のちがい,レベルのちがいなどに応じて,いろいろな対策をしめしている.
いずれかの原因,いずれかのレベルに特化して対策をしめしても,そこからはずれているひとには効果がないが,この本からはよりおおくのひとが自分にあった対策をみつけることができるのではないかとおもう. それができるのは,著者みずからがかつて 「やる気なし人間」 だった,たぶんそのときによっていろいろな原因やレベルを経験してきているからなのではないかとおもう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
やる気の法則@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,やる気の法則@Amazon.co.jp
,やる気の法則@Amazon.co.jp.
2008-08-26
生産者政策が重要なときに消費者政策? ― 周回おくれの日本の政策
日本では消費者政策がもっとももとめられていた時代には生産者中心の政策がすすめられてきたが,より生産者政策が重要になってきたいまになって,消費者庁の設立というような消費者政策を重視しているようにみえる. これはもしかすると日本にとって危機的な事態なのではないだろうか?
2008-08-23
著者自身がレガシーになってしまった?! ― 野口 悠紀雄, 遠藤 諭 著 「ジェネラルパーパス・テクノロジー ― 日本の停滞を打破する究極手段」
この本は今年 7 月に出版されたばかりだが,その論点のほとんどは 10 年以上まえから指摘されていることである. IT がジェネラルパーパス (汎用) コンピュータにささえられた技術であることは,この本でもふれている 1960 年代に登場した IBM のシステム 360 以来である. 日本の情報システムのおおくがレガシーである,つまりふるびたシステムをだましだましつかっていることも 20 年以上まえからである. 日本の電子政府が 「おもちゃ」 だという指摘はもっとあたらしいが,ちょっとつかってみればわかる程度の指摘でしかない. そして,これらの問題点に対する解決策はあたえられていない. それでいて 「日本の停滞を打破する究極手段」 などという副題をつけているのはあまりにひどい.
つまり,この本のもとになっている知識はだれでもすぐにしらべられる程度のものであり,結論 (になっていないむすび) もそうである. 著者自身がもうレガシーになってしまったということだろうか?
評価: ★★☆☆☆
2008-09-12
上昇しない食品価格 ― なぜ?
最近,原油や工業原料などとともに,大豆,小麦などの穀物価格も急騰している. そのため,小売価格も上昇しているという. たしかに,値上げされたものはすくなくない. しかし,大豆,小麦などを原料とする製品のなかには,価格がすえおかれたり,むしろ実質的に値下げされているものもある. 牛乳やジュースもあいかわらず低価格なものが売られている. なぜだろうか?
2008-09-23
ヴァーチャルからリアルへ ― 今後の技術の方向性
今後は,情報通信技術 (ICT) はこれまでのように主役であるよりも,農林水産業や鉱業の脇役としてのやくわりが増大していくでしょう. また,これらの 「リアル」 な産業に資金が傾斜する結果,ICT によるヴァーチャルな世界の重要性は相対的に低下するでしょう. サブプライム・ローン問題にみられるようなヴァーチャル世界のあやうさも,リアルへの指向をつよめるものとかんがえられます.
2008-09-30
有機食品や交配による食品などが対比されているが… ― グレゴリー E. ペンス 著 「遺伝子組換え食品」
食品に関する 4 つの見解である自然主義,科学的進歩主義,平等主義,グローバル主義のそれぞれに配慮しつつ,有機食品や従来の交配による食品の改良にも危険があり,遺伝子くみかえのほうが危険がすくないとかんがえられるばあいもあると論じている. 遺伝子くみかえよりはるかに危険なものとして狂牛病もとりあげられている.
全体としてとくに過激な議論はなく,遺伝子くみかえを正当に評価しているとおもう. しかし,1 章でいきなり有機食品への大腸菌や毒素の発生の問題が論じられているのには,いささかおどろいた. 有機食品を攻撃するのが目的ではないが,インパクトがつよすぎるようにもおもえる.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
遺伝子組換え食品@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,遺伝子組換え食品@Amazon.co.jp
,遺伝子組換え食品@Amazon.co.jp.
2008-09-27
ライブドア事件をみなおすきっかけとしてはよい ― 南堂 久史 著 「ライブドア・二重の虚構 ― 夢から覚めたという夢」
ライブドア事件はエンロン事件のような 「巨悪」 ではない,詐欺をはたらいたというのは錯覚だと主張している. そこまではただしいとおもうが,錯覚によって株価が暴落したから大損失が発生したという主張はうけいれがたい. 株価を左右する原因はさまざまあるが,それを錯覚といってしまっては,市場経済は錯覚のうえになりたっていることになるだろう. いずれにしても,ライブドア事件をみなおすきっかけとしてはよい本であるかもしれない.
評価: ★★☆☆☆
関連リンク:
ライブドア・二重の虚構@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,ライブドア・二重の虚構@Amazon.co.jp
,ライブドア・二重の虚構@Amazon.co.jp.
2008-10-17
くみたて家具のネジの梱包
くみたて家具にはネジ類が欠かせません. たいていは袋にはいっていて,しかも,たいていはびったりの数しかはいっていません. よく,かぞえまちがえないものだとおもいます. くみたて式のベッドを買いましたが,その部品は写真のようにパックされていました. これなら数をまちがえることはないでしょう. ちょっと感心しました.
2008-10-15
中国にきびしく日本にやさしい主張 ?! ― 谷口 正次 著 「メタル・ウォーズ」
レアメタル (希少金属) を中心に,世界で争奪戦をくりひろげる国や企業をとりあげている. 中心はレアメタルの主要な産出国でありながらアフリカなどから輸入している中国であり,低賃金,わるい労働条件,危険など,その悪評が執拗にかたられる. 日本では住友金属鉱山が積極的だというが,他国に負けるさまがえがかれている.
末尾では 「日本人が [中略] 話し合いを責任を持って行えば,少ない予算で短期間に成果を出せるだろう」 と書いている. この主張は理解できなくはないが,欧米や中国との対比はちょっと極端なのではないだろうか.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
メタル・ウォーズ@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,メタル・ウォーズ@Amazon.co.jp
,メタル・ウォーズ@Amazon.co.jp.
2008-11-11
ゲームのアイデアをあたためて事業化する “デジタルネイティブ” の少年 — アメリカならではの存在 ?!
11 月 10 日の NHK スペシャルでは,「デジタルネイティブ ~次代を変える若者たち~」 が放送された. もっともおおくの時間をさいていたのは,アメリカの 14 歳の少年,アンシュール・サマー (Anshul Samar) が自分でアイデアをあたためたゲームの仕事をネットで世界各地のひとに発注し,すでに 1000 万円をうりあげたという話である. 親がきいてもわからない方法で開発したということが注目されていたが,おどろくべきことはむしろ,その事業センスと,リアルな世界でもおとなと対等に議論しているところだとおもう.
2008-11-18
原油とその周辺の統計・予測にかぎった空論 (?!) ― 永濱 利廣, 鈴木 将之 著 「第 3 次オイルショック ― 日本経済と家計のゆくえ」
原油価格が一時は 140 ドルをこえた第 3 次オイルショックをさまざまな統計や予測によって分析し,第 1 次,第 2 次のオイルショックと比較している. 数値的に把握することは重要だし,過去のオイルショックと比較することで,現在およびちかい将来どう対処するべきか,ある程度の指針をえることもできるだろう.
しかし,現在の経済状況においては,原油だけでなく金属資源や農産物の価格高騰や,サブプライム問題からはじまった巨大なバブル崩壊とそこからもたらされる世界不況など,さまざまな要因がからみあっている. それに対してこの本はほとんど原油とその周辺に話題をかぎり,統計や予測の数値に説明をくわえる程度の分析にとどまっている. 他の要因をかんがえない予測にどれだけの意味があるのだろうか?
私自身もそうだが,一部のエピソードをべつにすれば,この内容が一般の読者の興味をひくものだとはおもえない.
評価: ★★☆☆☆
関連リンク:
第3次オイルショック@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,第3次オイルショック@Amazon.co.jp
,第3次オイルショック@Amazon.co.jp.
2008-12-10
経済水域を囲いこめ !?
日本の国土はせまいが,排他的経済水域は非常にひろい. 現在は不況のため石油も農林水産物も価格がさがっているが,いずれまた高騰するのはまちがいない. それをみこして,経済水域内の資源を他国にとられないようにするための制度や研究をすすめる必要がある.
2009-01-17
さまざまなひとのフェアトレードがまとめられている ― 長尾 弥生 著 「フェアトレードの時代」
1 人の著者が書いたことになっているが,実際は 20 人くらいのひとが書いた (or 語った) 内容をまとめている. この本を読んでもフェアトレードとはなんなのかがかならずしもわからないが,ひとによってちがうさまざまなフェアトレードに対するかんがえかたを知ることができる. 私自身は 「消費者が満足してこその生産があるべきで [中略] 「かわいそうだから」 という気持ちで買っても,使わないでタンスにしまわれているのは果たしてフェアなのだろうかと考えてしまうのです」 という 山口 絵理子 のかんがえに共感する.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
フェアトレードの時代@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,フェアトレードの時代@Amazon.co.jp
,フェアトレードの時代@Amazon.co.jp.
税金がむだづかいされる構造 ― 国家プロジェクトのばあい
これまで,いくつかの国家プロジェクトにかかわってきた. しかし,どうも,国家プロジェクトというものがすきになれない. しばしば税金がむだづかいされているとおもうからだ.
公共事業のむだづかいは糾弾されつづけてきたが,いまだにむだガネがつかわれている. 金額はそれよりちいさいとはいえ,同様のむだづかいはいたるところにあるだろう. むしろ,公共事業のように糾弾されていないがゆえに,もっとむだなカネがつかわれているのではないだろうか. 国家プロジェクトもそのひとつだとおもえる.
2009-01-13
マンションのセールスマンからの,みごとな電話
マンション屋から電話がかかってくることがおおい. 「マンションなどのセールスの手口とそれに対する感想」 という項目でそれを分析したが,最近は元気のないセールスマンがおおいようにおもう. なにが売りたいのか,なかなかわからない電話もおおい. そういうなかで,先日,大阪のセンチュリー 21 (Century 21) からかかってきた電話はみごとだった.
2009-04-23
アメリカ型資本主義を批判しつつ,かぎられた 「国富」 にとらわれている (?!) ― 原丈人 著, 「21 世紀の国富論」
シリコンバレーのベンチャー・キャピタリストである著者は,ベンチャーを殺すアメリカ型資本主義をさまざまな点で批判し,あたらしい資本主義をつくるべきだと書いている. サブプライム問題が発生してからはアメリカ型資本主義を批判する声はたかまったが,それ以前に書かれた本書は著者の目のたしかさを示しているといえるだろう.
しかし,それではこれからはどんな技術や産業がさかえるのか? 著者はそれを自身が提言している PUC (パーベイシブ・ユビキタス・コンピューティング) という概念にもとめ,それをささえるものとして IFX 理論 (インデックス・ファブリック理論) をあげている. しかし,それらは現在でもあまり知られていないままであり,今後ひろがるようにもおもえない. むしろ,本書ではまったくふれていない 「知識」 や 「知能」 の問題 (Web 3.0) がキーになるのではないだろうか?
著者は現在の情報機器のあいだでデータ構造がことなり互換性がないことを問題点としてあげている. しかし,とくに銀行の合併などで問題になる大規模なシステムの 「非互換性」 をもたらしているのは概念や文化のちがいである. こういう人間的な問題をかんがえなければ,将来有望な技術や産業をいいあてることはできないのではないだろうか?
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
21世紀の国富論@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,21世紀の国富論@Amazon.co.jp
,21世紀の国富論@Amazon.co.jp.
2009-04-29
理想には賛同するが,説得力がある議論だとはいえない ― 原丈人 著, 「新しい資本主義」
論旨はおなじ著者による 「21 世紀の国富論」 にちかい. 崩壊した金融資本主義を批判し,ベンチャー的ものづくりの価値を主張している. 著者はあたらしい産業には 「コア技術」 が必要だと主張しているが,自身が提言している PUC (パーベイシブ・ユビキタス・コンピューティング) という概念や,それをささえるものとして IFX 理論 (インデックス・ファブリック理論) からうまれることを期待している. Web 2.0 に関しては 「Web での第 2 世代のサービス」 としていて,その無理解にはおどろかされる. そして,開発投資の対象をきめるのに各分野の専門家がえらんだ企業に優先的に投資するしくみを提案している. マイクロクレジットというような途上国における起業のしくみや日本の途上国援助にもふれている.
タイトルの 「新しい資本主義」 とは 「公益資本主義」 だという. それをささえる経済学も組織的に研究しているというが,経済学がつくれたからといってそれを実現させるのは困難なことだろう. かかげた理想には賛同するが,説得力がある議論だとはいえない.
評価: ★★☆☆☆
関連リンク:
新しい資本主義@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,新しい資本主義@Amazon.co.jp
,新しい資本主義@Amazon.co.jp.
2009-04-28
「爪の垢を煎じてのむ」 本 ― 浜口 直太 著, 「コンサル成功物語」
なにごとも最後まであきらめない著者のすごさに圧倒される. あきらめないことは重要である. しかし,それによってほとんどの困難をのりきって成功させてきたのにはいろいろ理由があることが,この本を読めばわかってくる. そのひとつは人脈だ. 有名人をふくむ,ひとの信頼をえることが重要な要素であるようだ. 著者とおなじようにふるまうことはできないだろうが,「爪の垢を煎じてのむ」 に値する.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
コンサル成功物語@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,コンサル成功物語@Amazon.co.jp
,コンサル成功物語@Amazon.co.jp.
2009-05-02
混乱した状況のなかで自社における必要性を判断するためのヒント (?!) ― エリック・松永 著, 「クラウドコンピューティングの幻想」
著者は (経営) コンサルタントであり,顧客である企業の身になって提案やプロジェクト管理をしてきた. そういう著者からみると現在の 「クラウドコンピューティング」 のさわぎはシステムインテグレータなどが企業をふりまわしているようにみえる. 自社にとって真に必要なものはなにか,それをクラウドコンピューティングによって実現できるのかをみきわめる必要がある.
そのため,著者はクラウドコンピューティングとはなんなのか,1960 年代の TSS (タイム・シェアリング・システム) にまでさかのぼってみきわめようとする. また,クラウドコンピューティングの技術を分析し,さまざまな仮想化との関係も論じている. しかし,一般の企業ユーザにはこうした技術を理解する必要はないということもいっている.
Google と Amazon についてはかなりのページをさいて分析しているが,ほかに SAP, Oracle, IBM, 日本の各キャリアなどの企業の動向も分析している. 「クラウドコンピューティング」 が混乱した状況にある以上,かんたんな処方箋はない. こうしたさまざまな知識をえて総合的に判断することが経営者やコンサルタントなどには必要とされているのだろう.
評価: ★★★☆☆
2009-07-30
個人向けの話題にしぼればよかってのでは? ― 勝間 和代 著, 「会社に人生を預けるな ― リスク・リテラシーを磨く」
日本では個人も組織もリスクをとろうとしない. しかし,著者は,もっと積極的にリスクをとったほうが停滞をぬけだして,よりよい方向にむかうことができると主張する. そのこと自体にはまったく賛成する.
しかし,タイトルからわかるように本書はおもに個人にリスクをとることをすすめる本である. 組織のことにページをさけばさくだけ,個人としてはどうしてよいのやら,わからなくなる. 十分な情報があたえられていないので,「本書をきっかけに,[中略] ちょっとだけリスクを意識し,リスクを分析し,リスクを取ってみてください」 といわれても,とまどってしまうだろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
会社に人生を預けるな@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,会社に人生を預けるな@Amazon.co.jp
,会社に人生を預けるな@Amazon.co.jp.
2009-09-11
三公社までさかのぼって民営化を論じているが,批判的によむべし ― 石井 陽一 著, 「民営化で誰が得をするのか ― 国際比較で考える」
小泉郵政改革に反対する立場の議論である. 郵政や道路公団の民営化だけでなく,国鉄,電電公社,専売公社の民営化も批判的に再検討している. これら三公社の民営化に関しては累積赤字のツケを国民にまわしたことを批判している. しかし,そうしないで公社のままだったら,さらに累積赤字がつみかさなって,もっとひどいことになっていたのではないだろうか? これらの民営化に関する論点を提供している点では価値があるが,読者もこの本を批判的によむべきだろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
民営化で誰が得をするのか@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,民営化で誰が得をするのか@Amazon.co.jp
,民営化で誰が得をするのか@Amazon.co.jp.
2009-10-16
なかみよりさきにダメになるブランデーのコルク栓
ときどきブランデーをもらうのだが,それほど頻繁に飲んではいない. もらうときにすでにけっこう生産されてから時間がたっていることもあって,のむときには 5 年以上たっていることがある. それでもブランデーそのものは品質に問題はない. しかし,コルク栓はすでにぼろぼろになっていることがおおい. これはこまったことだ.
2009-11-28
チャンスは自分でつかめ ! ― 澤田 秀雄, 浜口 直太, 浅井 隆 著, 「100 年に一度のチャンス」
タイトルにだまされた. これからどうすればチャンスがつかめるか,そのヒントがえられるのではないかと想像したが,なにがどうチャンスなのか,わからずじまいだ. たしかに著者たちは 100 年に一度の経済状況でもうまくやっていけるのかもしれない. しかし,この本の読者はかれらからまなぶというよりは,自分でかんがえなければならないことを知るだけだろう.
評価: ★★☆☆☆
関連リンク:
100年に一度のチャンス@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,100年に一度のチャンス@Amazon.co.jp
,100年に一度のチャンス@Amazon.co.jp.
2009-12-30
具体例豊富な技術経営の本 ― 池内 紀 著, 「理系の企画力! ― ヒット商品は 「現場感覚」 から」
著者は技術経営の専門家だ. 技術経営の本というともっとアタマ・デッカチ (理論中心) の本を想像するが,この本では各章のタイトル (「法則」) はスローガン的になっているものの,内容は具体例に徹しているので一般向きだ. そして具体例を 「スローガン」 にうまくむすびつけている. しかし,具体例中心であるために読者が自分の仕事にこの本の内容をいかすのはむずかしくなっているともいえるだろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
理系の企画力@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
理系の企画力@Amazon.co.jp
,
理系の企画力@Amazon.co.jp.
2010-02-15
さわぎすぎのプリウスの 「不具合」
プリウスのブレーキの 「不具合」 が連日ニュースに登場してくる. トヨタによるとソフトウェアの問題だということだが,バグではないようだ. それにもかかわらず 「不具合」 とよぶことには違和感がある. ところが,「欠陥」 とよぶべきだという意見さえあるようだ.
2010-06-20
日本の没落への道をさししめす (?!) 本 ― 角川 歴彦 著, 「クラウド時代と 〈クール革命〉」
著者は経営者の立場にあって,「知のグローバリゼーション」,Web 2.0 やクラウド・コンピューティングへのながれを経験してきた. 「21 世紀の産業革命」 もアメリカからおこるなかで,日本は IT ではなく 「クール・ジャパン」,ガラパゴス文化を世界に発信していくのがよいという.
世間でいわれているいろいろなことをつなぎあわせた内容であり,著者独自のかんがえは希薄である. しいていえば,大衆文化が次世代をひらくというかんがえに独自性があるようにみえる. 著者は Twitter を評価し,「大衆自身がコンテンツを作り,公開することでウェブ空間に 「巨大知」 が形成され」 と書いている. しかし,Twitter が 「巨大知」 を形成できるメディアだとはおもえない. こういうひとの意見にしたがっているだけでは,日本はますます没落していくだろう.
評価: ★★☆☆☆
関連リンク:
クラウド時代と〈クール革命〉@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
クラウド時代と〈クール革命〉@Amazon.co.jp
,
クラウド時代と〈クール革命〉@Amazon.co.jp.
2010-06-28
○○リバブル = ○○ re-bubble ?!
「○○リバブル」 という不動産会社がある. あまりよい話題ではないので,あえて伏字にしている. 「リバブル」 は livable をカナがきしているのだが,re-bubble ともよめてしまう.
2010-07-02
失敗したくなければ著者のような専門家への依頼が必要 ?! ― 市村 博 著, 「なぜ 90%の人が家づくりに失敗するのか?」
家づくりの過程でのさまざまな罠について書いている. そのなかには施主がかかりやすい罠もあるが,おおくはハウスメーカーがかかった罠の話である. 施主も自分である程度それをチェックできるだろうが,おおくの点は専門家にチェックしてもらう必要がある. 著者はそういうチェックをすることを仕事にしている. そうは書いてないが,結局は家づくりに失敗したくなければ,こういう専門家にたのむ必要があるということになるのだろうか.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
なぜ 90%の人が家づくりに失敗するのか@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
なぜ 90%の人が家づくりに失敗するのか@Amazon.co.jp
,
なぜ 90%の人が家づくりに失敗するのか@Amazon.co.jp.
2010-09-10
潜入ルポはおもしろいが,するどい切り込みはやや欠ける ― 横田 増生 著, 「アマゾン・ドット・コムの光と影」
アマゾンに関する本は多々あるが,アマゾンの配送センタに潜入つまり勤務した経験を書いている本はほかにはないのだろう. ノルマのきびしさが強調されているが,これはアマゾンだけのことではないだろう. 潜入してはじめてわかることもいろいろ書かれているが,それほどおおきく目をひく内容でもない. なにか,もうすこし,するどい切り込みがほしかった.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
アマゾン・ドット・コムの光と影@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
アマゾン・ドット・コムの光と影@Amazon.co.jp
,
アマゾン・ドット・コムの光と影@Amazon.co.jp.
2010-09-11
非現実的な 「有事」 にもとづく食料安全保障論 ― 末松 広行 著, 「食料自給率のなぜ」
著者の肩書は 「農水省食料安全保障課長」 ということであり,この本のなかで自給率,消費構造,穀物価格や需給などに関してはさまざまな統計量がつかわれている. しかし,「安全保障」 のためには 「有事」 の際になにがおこるかを定量的に検証するのが重要なはずだ. ところがこの本のなかでは,食料輸入がすべてストップしたが国内生産はいままでどおりだったらどうなるか,というような非現実的な条件でおこりうることが検証されているだけだ. もっと現実的な条件でおこりうることはなにか,それにそなえるには自給率やその他の数値がどのくらいであるべきかを検証しなければ,食料自給がどうあるべきかを議論するには不十分だろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
食料自給率のなぜ@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
食料自給率のなぜ@Amazon.co.jp
,
食料自給率のなぜ@Amazon.co.jp.
2010-09-22
売り上げののばしかたにはくわしいが,編集についてはよわい ― アロン シェパード 著, 「私にはもう出版社はいらない ― キンドル・POD・セルフパブリッシングでベストセラーを作る方法�
通常の出版社をとおさずにオンデマンド出版の本をアマゾンで売ってきた著者が売り上げをのばす方法について書いている. 本の表紙のつくりかたやそれをどういうかたちでアマゾンにのせるか,「なか見! 検索」 をするべきかどうかなど,非常にこまかい (とみえる) 点が多々とりあげられている.
内容は売り上げをどうのばすかという点にかたよっているという印象をうける. 編集者の手をへずに出版するのだから,それにかわる方法論がもっとあってしかるべきだが,原稿をひとにみせてコメントをもらうという程度のことしか書いてない. そこがちょっと期待はずれだ.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
私にはもう出版社はいらない@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
私にはもう出版社はいらない@Amazon.co.jp
,
私にはもう出版社はいらない@Amazon.co.jp.
2010-10-23
「おもてなし」 をささえる裏方のしかけがおもしろい ― 内藤 耕 著, 「「最強のサービス」 の教科書」
加賀屋をはじめとする 8 つの事例を解説している. 「おもてなし」 とくふうをこらしたコストカットの両面をあつかっている. とくに,「おもてなし」 をささえる裏方のしかけがおもしろい.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
「最強のサービス」の教科書@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
「最強のサービス」の教科書@Amazon.co.jp
,
「最強のサービス」の教科書@Amazon.co.jp.
2010-11-09
「現場からの告発」 にしてはナマの情報がすくない ― 伊丹 敬之, 東京理科大学 MOT 研究会 著, 「日本の技術経営に異議あり ― 現場からの告発」
著者は大学の研究者なのに 「現場からの告発」 というサブタイトルがついているのは,フィールドワークにもとづく著書だからだろう. しかし,それにしては,ナマの情報がすくない. 内容がこなれすぎていて,やはり 「現場からの告発」 にはなっていない.
もとは章ごとに独立の文章だったようだ. 章ごとに著者がちがっていて,対象事業・業務はモノづくりもあればソフトウェア開発もあるが,章タイトルは事業・業務とは独立につけられている. よりひろく適用できる議論をめざしているということだろう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
日本の技術経営に異議あり@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
日本の技術経営に異議あり@Amazon.co.jp
,
日本の技術経営に異議あり@Amazon.co.jp.
2010-11-02
納得できる指摘 ― 町田 尚 著, 「「夢の新製品」 を生み出す 10 の鉄則」
「10 の鉄則」 すべてがピンときたわけではないが,ベンチャー企業において重要な点がふくまれいることはまちがいないだろう. 持続的な研究開発体制の確立,論文や特許の奨励など,自分の経験からしても納得できる内容だ. 経験はないが,「技術負債 [事故など] を返済するときは,負債を持っているチームにやらせないことが重要」 という指摘ももっともだ. 「新人社員が研究所を希望しているのならば,まずは研究所に配属させてやるのが良い」 というのももっともだが,なかなかできないことだろう.
評価: ★★★★☆
2010-12-21
モジュール化に関するさまざまな分析 ― 青木 昌彦, 安藤 晴彦 編著, 「モジュール化 ― 新しい産業アーキテクチャの本質」
工業製品が標準化された部品からくみたてられることは周知であり,その意味で 「製品アーキテクチャのモジュール化」 は目新しいことではない. しかし,この本ではそれだけでなく,「生産のモジュール化」,「企業間システムのモジュール化」がとりあげられ,また 「製品アーキテクチャのモジュール化」 においても日本の企業ではモジュール間のすりあわせをともなう,より柔軟なモジュール化がなされていることの指摘など,実際の生産の場の観察にもとづくさまざまな分析がなされている.
ただ,この本は章ごとにことなる著者が執筆しているため,それらの分析が十分に整理されたかたちでしめされていないところに弱点がある.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
モジュール化@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
モジュール化@Amazon.co.jp
,
モジュール化@Amazon.co.jp.
2010-12-16
読みおわってもモヤモヤしたものがのこる ― 平川 克美 著, 「ビジネスに 「戦略」 なんていらない」
タイトルをみると著者がビジネスに計画はいらないと主張しているようにもみえる. 実際,ビジネスにはゆるぎないゴールが存在したりせず,プロセスが重要だという主張をしている. しかし,目的や目標をたてることを否定しているわけではなく,それらは必要に応じて再設定するべきものだということだ.
著者がきらいなのは 「戦略」 という勝ち負けにかかわることばだ. 一方,著者はこの議論のなかにフェティシズムとか脱構築とかいうことばをもちこもうとしている. しかし,「戦略」 の否定をふくめて,十分に整理されているとはおもえない. 共感できる部分はあるが,読みおわってもモヤモヤしたものがのこる.
評価: ★★★☆☆
2011-01-15
多数の実例から読者も自分の戦略がみつけられる ?! ― クリス・アンダーソン 著, 「FREE フリー ― 〈無料〉からお金を生みだす新戦略」
「もっとも強力なマーケティング手法のひとつ」 つまり 「あるものをタダであげることで,別のものの需要をつくりだす」 のが 「フリー」 である. それは 19 世紀のおわりに誕生し,デジタル・メディアの登場でひろがった. Microsoft 対 Linux,Yahoo 対 Google など,この本ではさまざまな具体例をあげて,なぜタダにしてももうかるのかを説明している. この本のなかには 10 数個のかこみ記事があり,そこでさらにおおくの具体例をとりあげている. これらを読んでいくことで,読者も具体的な戦略をみつけることができるかもしれない.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
FREE@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
FREE@Amazon.co.jp
,
FREE@Amazon.co.jp.
2011-01-25
いまでも参考になる点があるブログ中心のクチコミについての本 ― コグレ マサト,いしたに まさき 著, 「クチコミの技術 ― 広告に頼らない共感型マーケティング」
2007 年に出版されたネットの本をいまさら読んだ. 当時はブログが話題の中心だった. 現在は事情がかわってしまった部分がおおいが,いまでもブログをかきつづけている私にとっては参考になる点が多々あった. 最近は 「炎上」 の話もあまりきかないが,炎上を解決するにはブログを閉鎖したりするのでなく真摯な姿勢が重要だという指摘は納得がいく. また,炎上しているときはふだんより注目されているからチャンスだという指摘ももっともだ. ブログの歴史もこれまで読んだ本にはあまり書いてなかったようにおもう.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
クチコミの技術@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
クチコミの技術@Amazon.co.jp
,
クチコミの技術@Amazon.co.jp.
2011-02-01
いたるところにある “アナログ・サイネージ” ― デジタル・サイネージの基盤 ?!
出張で St. Maarten (シント・マーテン,セント・マーティン) というまちにきて,まちなかをあるいていると,よく変化する広告看板をみかけた. 日本ではあまりみないものだ. 日本では最近,デジタル・サイネージがはやっているが,こういう “アナログ・サイネージ” の文化があるのとないのとで,デジタル・サイネージがうけいれられるかどうかがきまってくるのではないだろうか?
2011-02-04
あたらしい製品デザイン手法の紹介 ― それを体験できる場はあるか? ― 奥出 直人 著, 「デザイン思考の道具箱 ― イノベーションを生む会社のつくり方」
さまざまな企業からの依頼をうけて魅力的な製品をうみだしているデザイン会社 IDEO が話題の中心だ. GE, P & G, Apple などの会社にもふれている. そして,この本の中心は IDEO にみられる創造のプロセスの著者の体験にもとづく解説だ. そこでは,創造性は個人の才能ではなく方法でありマネジメントの問題だということ,プロトタイピングと,フィールドワーク,エスノグラフィーの重要性と手法などが記述されている. フランク・モスにひきいられる MIT メディアラボにおけるプロトタイピングの方法も記述されている.
こういうあたらしい方法はとくに日本の大企業にはうけいれられていないという. 会社がうけいれないなら,個人で経験する方法はないものかとおもう.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
デザイン思考の道具箱@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
デザイン思考の道具箱@Amazon.co.jp
,
デザイン思考の道具箱@Amazon.co.jp.
2011-02-19
President という名に恥じない特集 ― 「PRESIDENT (プレジデント) 2011年 3/7号」
ちかごろの President は,およそそのなまえとは相いれないことを特集していると感じてきた (以前はそうでなかったような気がするのだが…). 「年収 1500 万円の勉強法」 とか,「金持ち家族,貧乏家族」 とか,「いる社員,いらない社員」 とか,なんでこんなシミッたれたタイトルの特集を組むのか… そういう President がひさびさにそのタイトルに恥じない特集 「孫正義の白熱教室」 を組んだ. これならば,president (社長) から一般社員まで,いろいろまなぶことができる. 今後もこういう特集を期待したい.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
PRESIDENT@Amazon.co.jp.
2011-03-06
TPP に関しては反対の本ばかり…
最近,TPP (Trans-Pacific Partnership) に関する本が続々と出版されつつある. 菅政権によって急にもちだされた TPP 問題だが,賛成するにせよ反対するにせよ,急いで対処しなければならないわけだから,当然のことだろう. ところが,すでに出版されたり,ちかく出版されようとしている本はほとんど反対派のものだ. 賛成派はどこにいったのだろう?
2011-03-17
この本を読んで,頭をやわらかくしよう ― ジェイソン・フリード, デイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン著 , 「小さなチーム、大きな仕事 ― 37 シグナルズ成功の法則」
この本には,仕事を成功させるためのいろいろなちょっとしたアイデアや,かたい頭をほぐしてくれるようなことが書いてある. それがそのまま読者にやくだつことはむしろすくないだろうが,この本を読んで頭をやわらかくすれば,もっとうまくいくようになるのかもしれない.
評価: ★★★☆☆
関連リンク:
小さなチーム、大きな仕事@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
小さなチーム、大きな仕事@Amazon.co.jp
,
小さなチーム、大きな仕事@Amazon.co.jp.
2011-03-14
福島原発についての無責任な産經新聞の社説
3 月 13 日の産經新聞の社説では,今回の巨大地震がもとになって発生した福島の原発爆発事故がとりあげられている. タイトルは 「安全軽視が招く重大事態」 となっている. 内容を読んで唖然とした. とても,まともな新聞が書く社説だとはおもえない.
2011-03-08
TPP をあたまごなしに否定してはいない ― 廣宮 孝信 著, 「TPP が日本を壊す」
TPP が日本の農業をダメにし,デフレをもたらして国民に深刻な影響をあたえると主張している. しかし,TPP をあたまごなしに否定しているわけではなくて,TPP は劇薬だともいっている. つまり,うまくつかえば成功する可能性もあることを示唆している. それでも否定しているのは,菅内閣をはじめ現在の政治状況では成功のみこみがないときめつけているからだ. その政治状況がくつがえらないかぎり,TPP をとろうと,すてようと,日本は壊れるのではないだろうか.
評価: ★★★★☆
関連リンク:
TPP が日本を壊す@
![[bk1]](/weblog/bk1.png)
![]() ,
TPP が日本を壊す@Amazon.co.jp
,
TPP が日本を壊す@Amazon.co.jp.
2037-01-01
検索
カテゴリー
- Amazon (アマゾン)
- DIY (日曜大工) とものづくり
- Movable Type
- PowerPoint
- Web とインターネット
- Web 検索とその応用
- Wikipedia (ウィキペディア)
- eコマース (ネット通販)
- iPad
- iPhone
- voiscape
- くみあわせ問題
- インタフェース,アメニティとデザイン
- インテリア・家具・機器の博物館
- オペレーティング・システム
- オーディオ博物館
- グローバル化
- コンピュータ館
- セキュリティ・安全と秘密・プライバシー保護
- ソーシャル・ウェブとネットでのコラボレーション
- データベースとストリーム処理
- ビデオ・映画・テレビ
- ファッション
- フォントとレイアウト
- ブログ
- プログラミングとコンパイラ
- プロトコルとネットワーク
- マネー・電子マネーと景気循環
- メディア・アート・イベント・エンターテイメント
- リモコンのインターフェース
- 乗物と道路・駅
- 人工知能・複雑系と人工生命
- 仕事と起業
- 仮想化・仮想空間
- 住宅・設備
- 修理・修繕
- 健康・医療
- 共産主義・社会主義
- 動画サイトとビデオ・ストリーミング
- 商店街とまちづくり
- 国内旅行・出張
- 園芸
- 失敗
- 建築・都市計画
- 心理
- 思想・哲学・宗教
- 情報学・計算・プログラミング
- 情報通信博物館
- 戦争
- 放送
- 政治・法律・憲法
- 教養・教育と学習
- 散歩・まちあるき
- 文学
- 書評
- 未整理
- 未来の予測と創造
- 検索・抽出・組織化
- 構造改革と民営化
- 歴史
- 海外旅行・出張
- 災害・地震
- 環境・エネルギー
- 生活
- 産業・ビジネス
- 知的生産とリテラシー
- 研究法から生き方まで
- 社会・経済
- 私の Web サイト
- 科学・技術・自然
- 秘密・プライバシー保護とセキュリティ
- 箇条書き
- 若年者問題,ワーキングプアとプレカリアート
- 裁判員制度
- 視覚化・図解
- 観光・旅行・出張
- 言語・コミュニケーションとネットワーキング
- 語彙・訳語
- 読書法
- 農林水産業
- 道具
- 電子図書館・電子書籍
- 電話
- 音楽 (一般)
- 音楽評
- 食品と嗜好
- 高齢者対策と福祉サービス
Movable Type Pro 5.04