中学のころからオーディオに興味をもってきた私にとって,オーディオとは LP レコードを再生することでした. LP の再生のためには,いりぐちとなるカートリッジがまず重要です. 私はそこに Denon (電音) のカートリッジをつかいつづけてきました.
カートリッジには MM (Moving Magnet) 型と MC (Moving Coil) 型とがあり,製造や針交換の容易さなどの点で MM 型が優位ですが,音のよさでは MC 型に定評がありました.
私のばあい,最初につかったカートリッジは,ひとからすすめられた Denon の DL-103 でした.
オーディオが下火になるとともに,おおくのカートリッジ・メーカーは廃業していきましたが,DL-103 は NHK 指定のカートリッジとして,いまも生産されつづけています.
しかし,DL-103 は基本的には 1960 年代に開発された,ふるい技術にもとづくものであり,その後にさまざまな技術が開発されています. DL-103 じたいもそういう技術をとりいれて,さまざまなバリエーションがつくられてきました. MC 型のカートリッジは基本的に針交換ができません. したがって,針が摩耗するとカートリッジじたいを交換することになるのですが,交換するときにことなる機種に交換することもできました. そこで,私は DL-103 を DL-103S という機種に交換して,いまもそれをもっています. DL-103 は針圧が 2.5 g であり丸針がついていますが,LP にとっては針圧はひくいほうがよく,また丸針よりは 1970 年代に開発された特殊形状の針のほうがよい. DL-103S は針圧を 1.8 g にさげ,特殊楕円針をつけています. ただし,現在では生産されていません.
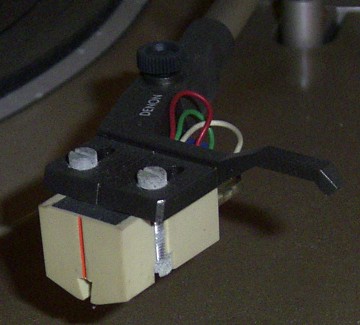 DL-103S
DL-103S
DL-103 / DL-103S は最初はトリオのターンテーブルとくみあわせてつかっていました (このベルト-アイドラー・ドライブのターンテーブルはもうのこっていません) が,DL-103S は Denon DP-32F に買いかえてからもつかいつづけました.
 DP-32F
DP-32F
3 台目のレコード・プレヤーとして Denon DP-37F を買ったとき,カートリッジとしてももうひとつ,べつのものを買うことにしました.
これが DL-301 です.
(このクラスのレコード・プレヤーにはカートリッジが付属しているのですが,付属していたカートリッジはつかったことがありません.)
改良版の DL-301II が現在でも販売されています.
DL-301 は針圧が DL-103S より軽い 1.5 g です.
家にはピアノ室兼リスニング・ルームがあるが,ピアノやオーディオをつかうとき以外はあまりつかっていません.
そのため,冬になるとこれらをつかうときだけ暖房をいれることになります.
そういうとき,DL-103S はあたたまるまで調子がわるかったのです.
針圧をややよけいにかけないと,びりつきやすかった.
これに対して DL-301 は低温にも比較的つよかったので,このへやでは DL-301 をつかってきました.
 DP-37F
DP-37F
 DL-301
DL-301
DL-103/S も DL-301 も出力レベルは 0.3 mV 程度であり,MC 型カートリッジとしては標準的です. オンキョーのアンプ A-817 GTR にはヘッドアンプがついているので,それをつかいはじめてからはヘッドアンプにつなぎました, しかし,真空管アンプ KA-1 をつかっていたときには,それに直接つなぐとノイズがめだつのはさけられなませんでした (それでも直接つないでいた時期があります). このアンプにつなぐには DL-103 専用のトランスをつかうのが順当です.
このように,トリオのターンテーブルをのぞけば Denon のカートリッジとレコード・プレヤーを買いつづけてきましたが,他社のカートリッジに興味がなかったわけではありません. ヘッドアンプなしにつなげて針交換が可能な MC カートリッジとしてサテンというメーカーのものがあり,ショウルームにききにいったりもしました.
また,当時 MC カートリッジといえば,国際的にはオルトフォンが有名でした. Fidelity Research (FR) の MC カートリッジにも興味がありました. いまでも MC カートリッジをつくりつづけている Audio Technica も当時から MC カートリッジをつくっていました. しかし,Audio Technica はさまざまな品番をつぎつぎにだすので,当時,私にはそのなかからえらぶのは困難でした. かぎられた型番のカートリッジをつくりつづけるコロムビア (現在はデノン) がえらびやすかったのです.
